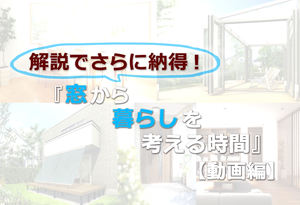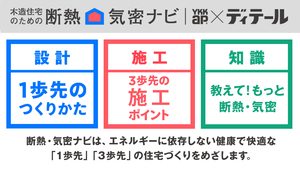今回のコラムは、今や当たり前と言われる「施工管理ツール導入」に関する仕事のあり方について触れていきます。
施工管理ツール導入が一般化する一方で、実はそのあり方の慣習が施工というプロジェクトを弱体化させ、更に個人スキルアップを低下させる間違った方向に進んでしまっている副作用も否めません。
確かに労働生産性が20年間で約1%しか向上しない建設業界においては、当然各社様々な角度から業務効率を上げ、限られた人材で上手く賄えるように工夫し、いかに安定させるかを目指されていくことは最重要課題であるに違いありませんが、本来の施工管理の目的に対して、適切な手段となっていないことが挙げられます。
このコラムでは、特にこれからこの業界で製造プロセスに関わっていく現場監督の方や、また設計者の方に是非ご理解いただけましたら幸いです。
まず、施工管理の体系を下の図表で概略を掴んでみてください。施工管理ですべき8つの役割を、着工前にすべき仕事と、現場ですべき仕事に分けて表記したものです。
この図表での「情報管理」という根幹に施工管理アプリ等を利用されているビルダー様がほとんどであると言って良いでしょう。
そして導入する側からはやはり一元管理していきたいでしょうし、情報を共有しながら、製造プロセスに対してエビデンスを残していきたいという目的も非常に理解できます。
しかしながら、情報管理における一番のリスクを考えてみましょう。
それは「情報の精度」です。
情報の精度によってはとんでもない「ムリ・ムダ・ムラ」を勃発させる大きな爆弾ともなり得るということを忘れてはなりません。ここで2つほど事例を挙げてみましょう!
事例①:設計図書のバージョン管理や変更が統制できていなかったら・・!
この ..
今回のコラムは、今や当たり前と言われる「施工管理ツール導入」に関する仕事のあり方について触れていきます。
施工管理ツール導入が一般化する一方で、実はそのあり方の慣習が施工というプロジェクトを弱体化させ、更に個人スキルアップを低下させる間違った方向に進んでしまっている副作用も否めません。
確かに労働生産性が20年間で約1%しか向上しない建設業界においては、当然各社様々な角度から業務効率を上げ、限られた人材で上手く賄えるように工夫し、いかに安定させるかを目指されていくことは最重要課題であるに違いありませんが、本来の施工管理の目的に対して、適切な手段となっていないことが挙げられます。
このコラムでは、特にこれからこの業界で製造プロセスに関わっていく現場監督の方や、また設計者の方に是非ご理解いただけましたら幸いです。
まず、施工管理の体系を下の図表で概略を掴んでみてください。施工管理ですべき8つの役割を、着工前にすべき仕事と、現場ですべき仕事に分けて表記したものです。
この図表での「情報管理」という根幹に施工管理アプリ等を利用されているビルダー様がほとんどであると言って良いでしょう。
そして導入する側からはやはり一元管理していきたいでしょうし、情報を共有しながら、製造プロセスに対してエビデンスを残していきたいという目的も非常に理解できます。
しかしながら、情報管理における一番のリスクを考えてみましょう。
それは「情報の精度」です。
情報の精度によってはとんでもない「ムリ・ムダ・ムラ」を勃発させる大きな爆弾ともなり得るということを忘れてはなりません。ここで2つほど事例を挙げてみましょう!
事例①:設計図書のバージョン管理や変更が統制できていなかったら・・!
この ..A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。